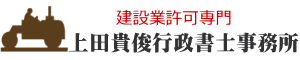社会保険の未加入業者に対する指導方法についてまとめています。元請が下請けに加入を促すことは当然ですが、1次下請け業者がさらに2次下請けに出す場合は1次下請け業者も加入指導をすることが求められます。元請の加入指導への協力義務という形で行います。工事を下請けに出す事業所者はこの記事を読み、具体的な協力方法について確認してください。
※令和2年から適切な社会保険に加入していることが建設業の許可要件になりました。つまり未加入だと指導されるという問題ではなく建設業の許可を取得・継続出来なくなります。詳しくは建設業許可の要件化!社会保険の加入は必須|建設業法改正でご確認下さい。
平成29年度には適切な社会保険に加入していない作業員を現場に入場させない等、未加入業者への取締がいっそう厳しくなる見込みです。
社会保険は行政庁や社会保険局が建設業者に直接加入する指導を行うのみならず、元請業者が下請け業者などに加入指導をさせるなど民間事業所間にも加入指導義務を課してしています。
元請業者は下請け業者が社会保険に加入しているかを把握する義務があることは当然です。
しかし元請だけなく下請業者に対しても自社の請負工事を施工する下請業者で社会保険未加入業者に対して加入指導を行わなせるガイドラインが存在します。
この記事を読み、建設業許可取得後の下請け業者として行うべき社会保険加入指導の具体例を確認しましょう。
指導方法
元請業者は請け負った工事について幅広く責任を負っています。
このことから元請業者には下請業者に社会保険に加入する指導や助言を行う努力義務が課されています。
指導対象となる下請け業者は直接の契約関係にある下請け業者のみならず2次、3次も指導対象です。
そしてこの指導は直接の契約関係にある下請け業者に協力させて統括するという方法でも良いとされています。その場合、下請業者は元請業者へ協力義務が発生します。
下請業者は具体的に何をすればいいの?
下請業者が行うべき対応は次の通りです。
1つずつ確認しましょう。
①自社が未加入であれば、社会保険に加入する
これは当然ですね。
②元請業者に対して下請業者の社会保険加入状況に関する書類を届け出す
具体的な書類としては「再下請負通知書」と「作業員名簿」が挙げられます。
再下請負通知書
再下請負通知書とは一次下請けの事業所が2次下請けと請負契約の詳細について元請に報告する書類です。
この中の項目の1つの『健康保険等の加入状況』を記載して提出します。ちなみに2次下請けがさらに3次下請けした場合は二次下請け業者が再下請負通知書の作成義務が生じます。
未加入業者がいれば元請は加入指導義務がありますので、指導する必要があります。
作業員名簿
作業員名簿とは建設工場の現場で働く労働者の新規入場者の受け入れを管理するための名簿です。
事務員などは含まれていません。作業員のみの名簿になります。その名簿の『社会保険関係』欄で適切な社会保険に加入しているかを確認します。
事業所と従業員の雇用関係を明確にした上で適切な社会保険に加入していなければ指導対象です。
適切な社会保険とは?
厚生年金、健康保険、雇用保険を指します。
例えば法人に属する常勤の作業員であれば必ず厚生年金と協会健保等の健康保険への加入義務があります。健康保険に関しては自治体管轄の国民健康保険に加入しているだけといった場合が適切な保険に加入していないということです。
社会保険加入義務の有無はこちらの『社会保険に加入義務がある建設業者の要件と申請確認書類』をご覧ください。
③工事に関係する全ての事業所に社会保険加入の指導が行き渡るようにする
元請の加入指導に協力します。
自社はもちろん、2次下請け、3次下請けに対して作業員を適切な社会保険に加入するように指導することです。
まずは口頭による指導ですが、最終的には文書による指導を行うことが一般的です。
 ・民間の事業所も社会保険の加入指導をすることが求められている
・民間の事業所も社会保険の加入指導をすることが求められている・平成29年から適切な社会保険に未加入の労働者は工事現場に立ち入らせない
・元請から管理を頼まれた1次下請けは協力義務が生じる
・下請け業者の協力義務は大きく3つあげられる
まとめ
令和2年から建設業の許可要件に社会保険の加入要件が新設されました。
それまでは社会保険に加入していなくても許可は取れましたが、なるべくなら社会保険に加入させたいということで未加入業者への指導の取扱が設けられていました。
今では社会保険への加入が要件化したこともあり未加入業者は減りましたが、もし加入義務があるのに未加入業者がいれば加入するよう指導していただくことが望ましいです。