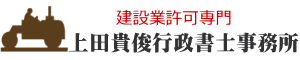個人事業主で建設業の許可を受け、家族と一緒に事業をしている方またはこれから許可を受ける予定の事業者向けの記事です。許可を受けた個人事業主が引退後も許可を継続させる場合の注意点がまとめられています。具体的に息子(子供)や配偶者を経営業務の管理責任者として認められる条件などが書かれています。将来的にも事業を継続していきたい場合、法人化を含めて検討すべき手続きをご確認ください。
このページをご覧になっている方は
個人事業主として既に建設業の許可を取得していて、すぐにでも家族に許可を引き継がせたいと悩んでいる方ではないでしょうか。
また、これから許可を取得したいけど子供に許可を引き継ぐことを考えると、個人事業主ではなく法人にしてからの方がいいのではないか?と中長期的な目線で悩まれていませんか。
もし家族で経営していていれば従業員はご家族のみになります。
ご家族の従業員としての経験が許可要件を満たせるかが大事です。
自分がいなくなっても許可を継続させるためには、ご家族の方だけで建設業の許可要件を満たすためにはどうすればいいのか確認しましょう。
この記事を読むことで家族経営の事業主が建設許可を継続させるための方法を知ることが出来ます。
Contents
家族経営の個人事業主
法人と比べて個人事業主が建設業の許可を継続させることが難しい理由は大きく2つあげられます。
一つずつ確認しましょう。
正式な書類が残っていない
家族経営となると、正式な書類を作成しない、残していないということはよく起こり得ます。
家族経営の方が組織図とか業務分掌規定等作成する方が少ないというのはイメージがつくのではないでしょうか。
後述しますが、業務を補佐した経験が6年以上あれば経営業務の管理責任者の要件は満たせます。
この補佐した経験とは経営業務の管理責任者の仕事を補佐した業務経験を指し、個人事業主であれば奥さんや子供が手伝っていれば該当します。
ただし、この補佐した経験を証明するためには当然、そういった書類が残っていることが必要でです。
どの書類があれば問題ないということは断言出来ませんが、少なくとも期間分の給与明細は残しておきましょう。そして一般的な基準と比べて多く給与を受けていることが望ましいです。
経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を証明が難しい
実務経験で専任技術者になる場合を考えましょう。
法人であれば社会保険の加入期間で専任技術者の常勤性を証明出来ます。
しかし個人事業主に雇われていた場合には、法人と違い社会保険への加入義務がないので常勤性の証明が困難です。
経営業務の管理責任者の経験も比較しましょう。
経営業務の管理責任者の要件証明も法人であれば取締役に就任した期間と明確な基準があります。
しかし個人事業主の期間で証明する手段が専従者欄に名前がある、業務を補佐した経験、支配人登記をしていた期間のいずれかです。いずれも取締役の就任期間を証明するのと比べると難しいと言えます。特に支配人登記はメジャーではないので登記している方は少ないです。
以上、法人より個人事業主が許可を引き継ぐことが難しい理由でした。
家族経営の事業者が建設業許可の要件を満たすためには
個人事業主が法人と比べて許可を引き継ぐことが難しいことはわかりました。
では具体的にどんな方法で許可を継続できるのか確認しましょう。
経営業務の管理責任者としての経験
建設業許可の要件の1つに『経営業務の管理責任者(以下、経管)としての経験』があります。
この要件を満たすためには事業主としての建設業の請負工事の経験を証明する必要があります。
経営業務の管理責任者(経管)について詳しく知りたい方はこちらからご確認ください。
・建設業許可の経営業務の管理責任者とは?通称、経管を徹底解説!
個人事業主本人が経管を証明するためには確定申告書の控え(受付印済)が必要です。ただし確定申告書で経管の経験が認められるのは個人事業主の本人のみです。奥さんや子供に経管としての経験証明には別途書類が必要です。
よって次の方法で証明します。
一つずつ確認しましょう 。
①確定申告書の事業専従者欄に奥さん・子供の名前を書く
個人業主であれば毎年確定申告書を提出します。
そこに専従者を記載する欄があり、そこに名前があれば経営業務を補佐したものとして認められます。
ここに名前を書くことで、公的な書類として子息は建設業の経営に携わってたと認められます。この経営に携わってた期間が6年あれば経営業務の管理責任者の要件を満たせるわけです。
専従者として名前が6年間確認出来れば、経管と同等の能力があると認めるという制度です。
ただしのこの方法で経管を変更するためには、個人事業主 本人から世代交代でないといけません。どういうことかと言うと、事業主が亡くなった場合には該当しないと言うことです。この場合はまた別の事業承継といった形での申請になります。
まとめます。
確定申告書の事業専従者欄に息子(配偶者)の名前を書くことが建設業許可を継続するための対策として挙げられます。
②支配人登記をする
登記と言えば法人のイメージが強いですが個人事業主にもあります。
それが支配人選任登記です。
支配人とは特定の営業所の事業について裁判上 ・裁判外の一切の行為を事業主に代わって行う権限を有した者です。
つまり第三者に対して事業主相当の権限を有する=支配人と言うことです。
この支配人としての経験は経営経験にカウント出来ます。よって支配人登記された期間と建設業の経営経験期間が5年以上証明出来れば、その者は経営業務の管理責任者になれると言うことです。
もし将来的に許可を引き継ぐことが確定しているのであれば、権限を与えた上で支配人登記をしておくことも対策としては良いかもしれません。
また、もし個人事業主本人が経営業務の管理責任者の要件を満たせなくても、要件を満たした者を支配人登記をした上で迎え入れることも可能です。
 ・確定申告書の控えは必ず保存する
・確定申告書の控えは必ず保存する・確定申告の事業専従者欄に息子か配偶者の名前を記載することが、後継ぎの際に重要
・経営を補佐した経験が6年以上あると認められれば経管となれる
・家族に権限を与え支配人として5年間登記をすることを許可を引き継ぐことが出来る
③6年以上業務を補佐した経験を証明する
経管の要件に経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年間以上経営業務を補佐した経験とあります。
この経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、大きな会社であれば執行役員が該当します。執行役員とは従業員の立場で取締役会から権限の委譲を受けて建設業部門の執行機関として経営管理を行う者です。
執行役員であることを証明するためには、執行役員規定や組織図、稟議書等が必要になります。
しかし小規模事業主や家族経営の会社だと、実際には執行役員的な立場で仕事をしていたとしても、上述した資料を作っていないことが多いです。
よって、個人事業主や役員に次ぐ地位で業務を補佐した経験が6年以上ある者は執行役員でなくても経管として認めるという制度があります。
家族経営の個人事業主の場合は、奥さんや息子が該当することが多いです。
補佐していた経験の代表的な行為は次のものです。
6年間の経営の補佐経験があれば経管の要件を満たせます。補佐経験とは具体的には何を指すのでしょうか。
これらに従事した経験を指します。
何かしらの経営管理に携わってきたことを書面で証明します。稟議書であったり決裁書などがそれです。
とはいってもズバリの書類がないこともあり得ます。
そういう場合に重要なことは給与の多さです。
役割が重要(経営者に近い)なので、給与を多くもらっていると言うことは一般論としては言えるでしょう。もちろん給与が多く支払われていると言う根拠だけで給与を補佐したとは認められませんが、補佐をしている立場にある者だろうという推定は働きます。
給与の支払い歴と業務分担が分かる書類が6年分揃えば証明出来る可能性はぐんと高まると言えるでしょう。
補佐した経験の証明書類
補佐した経験を証明するための書類は次のものと言われています。。
経管を補佐した者の名前が書いてることが必須です。
専任技術者の要件
個人事業主が専任技術者を兼ねていた場合、別の者を専任技術者として立てる必要があります。
もし引き継ぐ家族の中に有資格者がいれば、その方を常勤性がある形で雇えば問題ありません。
しかし資格がない場合には実務経験を有する者が必要です。理系の学校を卒業していなければ最低10年間の実務経験を証明しなくてはいけません。
さらにその実務経験はその期間中の常勤性が必要なので最低10年間の常勤性を証明しなくてはいけません。
言い換えれば次の書類を10年間分準備する必要があると言うことです。
これら原本で必要です。
もし10年間の実務経験であれば10年間分必要になります。
住民税の特別徴収決定通知書とは普段お支払いする給料から住民税を天引きする額を事業主に通知した書類です。主たる給与を支払う事業主にしか発行されない書類なので、特別徴収決定通知書があればその事業主の元で労働していたことが伺えると言う意味合いです。
賃金台帳とは給与の支払い履歴みたいなものです。この給与が一般的な給与として十分に支払いを受けていれば常勤性として認められる可能性は高くなります。
賃金台帳は労働基準法で作成することが義務付けられている帳簿です。ですが、賃金台帳だけだと本当に支払ったか真偽性を問われるので銀行通帳の取引記録と合わせて確認出来ることが望ましいです。
まとめ
家族経営の個人事業主が許可を引き継ぐために必要な方法につきまとめました。
普段から書類を整備しておくことが望ましいことは言うまでもありませんが、家族経営となると書類を保存しておくということに意識が向かないと思います。
いざ、許可を引き継がせたいというタイミングで書類が揃わず証明出来ないということはもったいないことです。
なるべく書類は保存しましょう。
中長期的に出来ることは次の通りです。
言い換えれば10年間分、次の書類を準備する必要があると言うことです。
正直、手間がかかる手続きだと言えます 。もしなるべく安全に引継ぎたいのであれば個人事業主より法人の方が容易です。
詳しくは次の記事をご覧ください。
・法人成り|建設業許可を取得している個人が法人化する際の注意点
また今回お話をしたことは世代交代として許可を引き継ぐ場合のお話です。
もし個人事業主が亡くなって許可を継ぎたいとなると、別の手続きが必要です。
詳しくは別の記事で解説します。
ご不明な点があれば専門家にご相談ください。