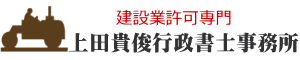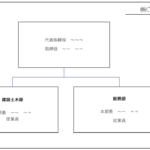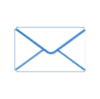最近、機械を取り扱う商社からよく建設業許可の連絡をいただきます。
「実は今まで弊社がやってきた機械を仕入れて、お客さんに収める商売は建設業なのでしょうか。」
結論からいえば建設業に該当するものが多いといったところでしょうか。
では建設業に該当したとします。
すると残念ながら芋づる式に建設業に関する法違反が見つかってしまうんです。
それは建設業という特殊な産業故に起きてしまうからです。
そこで今回は機械を取り扱う商社が無意識に違反してしまうことをまとめます。
Contents
その前に
このコンテンツを御覧頂いている方はそももそ工事って何?って思っている方もいるかもしれません。
しかしこれは具体的な定義が建設業上あるわけではありません。
建設業法では建設工事を請負う営業のことを建設業と定義しているからです。
なので私が今まで商社の方とお話してきたことをまとめると、本記事の対象者はイメージとしては一次側に接続しないと機能しない機械を販売している方が対象とお考え下さい。
この一次側に接続するという作業が機械を動かすためには必要で、契約の中に接続済の状態で引き渡すことが含まれていれば建設業に該当すると行っても問題ないのが私の考えです。
商社が違反しがちな建設業に関する違反
商社が違反しがちな建設業法に関する代表的な違反は次の5つです。
それぞれ確認しましょう。
①無許可営業
建設業法では税込500万円超の工事を請負う場合には許可が必要です。
となると機械を取り扱う商社が契約する工事の案件はほとんど建設業法違反にあたり、無許可営業に該当します。
なぜか。
それはこの500万円には機械器具代金が含まれるからです。
商社の方々は商習慣からか機械器具代金を除いて作業代金のみで500万円に達していないので問題ないとご判断されていますが、そうではありません。
根拠は建設業法施工令のこの部分です。
建設業法施行令 第1条の2建設業法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事(許可がなくても問題ない工事)は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
機械部分は3項の材料を提供する材料に該当します。よって500万円には材料費つまり機械代金込みで判断しないといけないわけです。
中には、設置作業は弊社がしておらず下請業者に任せている。うちは商品を卸すだけだという会社もありますが、そうであったとしてもダメです。
建設業法上、この商社は発注者(エンドユーザー)と直接契約交渉するため元請業者に該当し、契約を履行するために下請業者へ作業を依頼していることになります。つまり工事を施工管理している立場になります。施工管理していないのであれば一括下請の禁止に該当や配置技術者違反に該当して建設業法違反です。
②元請業者としての義務違反
建設業法上、元請業者は義務を課せられています。
他業種と比べて現場毎に多重層構造で作業が行われるという特殊性から安全面や施工管理上の責任者を定めるためです。よってその果たすべき責任を建設業や労働安全衛生法で定めています。
物品販売業という認識であれば基本的には果たせていないことだらです。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
③一括下請の禁止
①の無許可営業で軽く触れましたが、建設業法では一括下請を禁止しています。
簡単にいえば工事の丸投げです。
建設業法では現場に技術的な責任者を現場に専任させることが義務付けられています。その技術的な責任者を監理技術者や主任技術者と呼びます。(以下、主任技術者等)
主任技術者がいない中で設置作業を下請業者にさせて、マージンだけもらうというような収益構造になっていませんでしょうか。これが一括下請けの禁止に該当します。
また商社の商行為にある支払代行(注文書の取次、支払い)は正に建設業法の一括下請の禁止に該当するというのが私の意見です。
罰則としては無許可業者にはありませんが、結局無許可営業に該当することがほとんどなのでしていはいけないと言えるでしょう。
④労働安全衛生法違反
労働安全衛生法とは従業員が工事現場等で危険な目に合わないようにするための安全基準の最低基準を定めた法律です。
建設業は特に危険な業種と指定されており、その中でも元請業者には現場の責任者として安全基準を満たせるよう色々な義務が課せられています。
この安全基準を満たすためには、まず自社の業務が建設業に該当するという認識を持つところから始まります。
労働安全衛生法は労働基準法から派生された法律なので、遵守していない場合には刑事罰(罰金刑がほとんど)です。
現場で事故があった際には司法権限のもつ公務員が検査をして事業主を検察に書類送検することがあるので注意が必要です。
また昨今はアスベスト関連の法令がどんどん厳格化されていっております。ドリルで穴を開ければ建設工事判定されるため機械を取り扱う元請業者はコンプライアンス上無視することはできません。詳しくは下記からご確認下さい。
⑤労災保険料の未払い
商社に限らずオフィスでも毎年一労働保険料は支払っていると思います。
しかし建設業の現場ではオフィスではなく工事現場です。よって建設業は労災保険の取り扱いにおいても、特殊な取り扱いが求められています。
簡単に言えば、現場ごとに元請業者が下請業者の作業員までの分もふくめて労災保険の手続と保険料を支払う必要があるということです。
つまり現場で事故があれば、被災者が自社以外の作業員であっても元請業者が療養補償給付や休業補償給付などの手続をする必要があります。もし事故がおきた後にうちは関係ないというのは無しです。
建設業の元請業者に該当するのであれば労災保険の支払と手続は義務があるということです。
まとめ
いかがでしょうか。
商社が自社の提供するサービスが物品の販売だけではなく、建設業にも該当するとなった場合に芋づる式に法違反が発生するということご理解いただけましたでしょうか。
昨今は仕入先が無許可業者には機械を販売しないといったケースも行わているよで、それがきっかけで弊所に連絡が来ることも少なくありません。
もし発注者に下請業者が現場で機械を組み立て一次側に接続する作業を含みサービス提供をしているのであれば、建設業に該当するため許可の所得をご検討下さい。
とはいいますが、機械を取り扱う多くの商社が建設業許可の中に機械器具設置工事業という業種の許可が必要になりますが、取得することが難しいのです。
それも機械器具設置設置工事業といって比較的許可取得が難しい業種に該当することが多いです。難しい理由としては営業所専任技術者になるための証明が難しいということです。
取得できる国家資格が限定的なので実務経験で取得しないといけません。実務経験で取得する場合の説明は別記事に委ねますが簡単ではないということだけご理解下さい。
くわしくはこちらの記事を御覧ください。
また商社様、機械メーカー様向けに作成した建設業法違反しがちなケースをPDFファイルにて配布しています。
こちらも社内の会議等でご活用ください。
いずれにせよ、遠くない将来に建設業許可が持っていないと取引できないということは起こると思っています。
理由としては商社が円安もあり業績が好調なため業界全体でコンプライアンス意識が高まるからです。危ない橋を渡らずに取引をしたい仕入先や発注者は増えていくと考えております。こちらが私見です。
もしほかの行政書士に相談したが許可取得は難しいと言われ困っておりましたら弊社にお問い合わせください。色んな選択肢を考えて許可取得に尽力いたします。
お疲れ様でした。