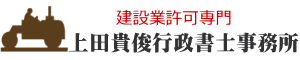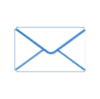実際に顧問先やお問い合わせいただいた質問をベースに行政書士の上田が回答をしたことをコンテンツにまとめています。
守秘義務の関係上、若干脚色はありますがご了承ください。
Contents
質問内容 『専任性が生じる主任技術者が他の工事の非専任工事に従事することは可能でしょうか?』
配置技術者の専任期間についてご質問です。
監理技術者制度運用マニュアルより、以下2点の、他の専任工事に従事する場合の記載がありました。
①(元請の場合)発注者の同意があれば、発注者が同一の他の工事の専任技術者として勤務
②(下請の場合)発注者、元請、上位の下請の承諾があれば、発注者、元請及び上位の下請のすべてが同一の他の工事の専任技術者として勤務
この意味することは請負金額が税込み4500万以上の建設工事の主任技術者は、専任を要しない期間中は他の非専任工事に従事することは可能ということでしょうか。
例
弊社元請、請負金額4500万円の建設工事、主任技術者A氏を配置、契約工期4月1日~4月20日(専任を要しない期間、4月15日~18日)
A氏は、施主が異なる別の工事に(請負金額1000万円、契約工期4月15日~4月18日)主任技術者として勤務は可能ですか
上田からの回答 「基本的には不可ですが、、」
ご質問にある監理技術者制度運用マニュアルでは専任性が生じる工事であっても、専任制を要しない期間を確認しましょう。
具体的には次の4つのケースに該当し、計画書などの書面で明確に記載されていることで該当します。
1. 「専任が不要となる期間」の具体例
例① 工事用地等の確保ができていない期間
着工できる状態に至っていないため、現場での施工が一切行われないケース。
例えば、行政の許認可が下りず工事用地が明け渡されていない・資材搬入ができない等。
この期間は、主任技術者(または監理技術者)の常駐が実質的に不要と見なされる。
例② 自然災害や埋蔵文化財調査等で工事が全面的に停止している期間
地震・大雨・台風などにより工事現場が安全に作業できない状態が続いている場合。
埋蔵文化財が発見され、調査が完了するまで現場を掘り返せないといった状況も含まれる。
いずれも「発注者の指示」や「不可抗力」により、作業が一切進められない期間。
例③ 工場製作のみが行われている期間
橋梁やポンプ、ゲートなどの機器を工場で製造しているが、現場での据付・施工がない期間。
現地工事は後の工程で始まるため、現時点では専任の技術者を現場に常駐させる必要がない。
例④ 工事完成後、検査が終了し、事務手続や後片付けのみが残っている期間
現場施工としての作業はほぼ終了し、検査後は書類整理や軽微な後片付けのみという状態。
実質的な施工が伴わないため、専任で常駐するほどの管理業務は要求されない。
ここをまとめたコンテンツは配置技術者の専任性を要しない期間に重複配置は問題ない?元請業者向け からご確認ください。
2. 「他の工事」に従事が認められる具体例
監理技術者制度運用マニュアルには、「専任が不要となる期間」に同じ発注者が行う別工事へ配置技術者が移ることを認める例が明記されています。
代表的なのが以下の2パターンです(短い引用):
①(元請の場合)発注者の同意があれば、発注者が同一の他の工事の専任技術者として勤務できる
②(下請の場合)発注者、元請、上位の下請の承諾があれば、発注者・元請・上位下請が同一の工事に専任技術者として勤務できる
この規定は「同じ発注者または同じ元請」という条件が大前提として書かれています。
一方、今回のご質問にあるような「発注者が異なる工事」を兼務するケースについては、運用マニュアルについてはかなり限定的なケースとして記載があります。結論だけいえば全く関係ない工事だったら発注者や注文者が違うならNGということです。
よってご質問へ回答するのであれば基本的には不可になる。ということです。
3. 例外に該当するか
とはいえ建設業も人手不足のため、配置技術者の要件も拡大され緩和されていっています。
大きく次の2つです。
詳細はリンク先を御覧ください。今回のご質問の工事が上記に該当して要件を満たすのであればマニュアル内の専任制を要しない期間といったことは関係なく兼務可能です。
行政書士・上田の私見
よって回答としては不可ということになるのですが、計画上、元の現場は専任性を要しない期間と承諾がとれているのにも関わらず、他の工事に従事することに対してそれほど条件を限定的にするのはどうなんだろうと個人的に思っています。
上述したように例えば監理技師補がいてい通信環境が整っている場合や工事現場の移動が概ね2時間以内であれば認めるといった緩和措置が導入されていったのは説明した通りです。
建設業法の目的の一つは発注者の保護なので、一定以上の有資格者の専任性という形で請負契約を発注者と結ばせることのは合理的な規定と思えます。
ただ「専任不要の期間=法的には常駐が義務づけられない期間」であるが、他の工事には関与してはいけないってどうなんですかね。
あくまでも工事全体が動かない、または現場の施工がない状態であること
発注者との合意をきちんと取っている
専任を要しない期間中に必ず終わる請負工事
これらの工事の要件を満たせば、発注者が異なる他の工事(非専任性)に従事してもいいとなっていくのではないかと思っています。
またややこしいことに監理技術者のマニュアルも次のような記載になっています。
元請の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐については、前述の工事現場への専任を要しない期間1)から4)のうち、
2)(工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間)に限って、発注者の承諾があれば、発注者が同一の他の工事(元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る)の専任の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐として従事することができる。
この日本語を皆さんはどう読み取りましょうでしょうか。
結論からいえば2以外は発注者が同一だろうと他の工事に従事することはできないということのようです
ただここだけ読めばケースの2)だけが発注者の同一要件としてよみとれますよね。
私としては「専任を要しない」期間は現場に文字通り専任(その職務のみしかしてはいけないこと)しなくよいわけですから、その期間中に完了する別の発注者の工事(非専任レベルの工事)の主任技術者として配置することが即問題になるという考えを持っていません。
「専任が不要の期間中に別の発注者の工事現場で非専任として業務を行い、その工事が専任不要期間中に完了する。専任性を要しない工事の発注者とも上記につき承諾を得て書面を締結している」
このような状態であれば建設業法の発注者保護の精神にも則っていると考えられるため、差し支えないと考えられるのではないでしょうか。
ただしあくまでも私見ですので、実際に行う場合には許可行政庁にも具体例の下で判断を仰いでみてください。
4. まとめ
監理技術者制度運用マニュアルには、専任不要の期間として「工場製作のみ」「工事の全面停止期間」「検査終了後の残務のみ」などの具体例が示されています。
その期間中は「他工事の配置技術者となる」ことを認めるルールも記載がありますが、基本的には**同じ発注者**が前提です。
発注者が異なる場合の明文例は少ないものの、現場が実質的に止まっているならば、「専任義務が発生していない=他の工事に行っても支障はない」と解釈したのが上田の意見。
とはいえ簡単に行動に移すのではなく、発注者との同意が得られない・書面で停止期間をはっきり示していない・急な再開に対応できないなどのリスクがあるため、運用時には十分な調整と誤解が無いように書類整備はもちろん、許可行政庁にも具体例を添えて確認してください。法の趣旨は発注者の期待を裏切らないようにすることです。