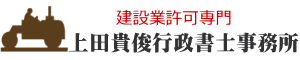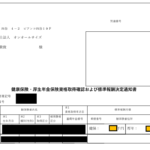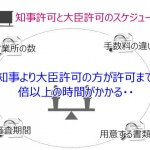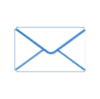建設業許可を維持するためには許可要件を維持し続ける必要があります。
その許可要件の一つに常勤役員等があります。経営業務の管理責任者(経管、けいかん)と呼ばれていたものですね。
この常勤役員等は役員の中に建設業の経営経験を一定年数以上有する者が常勤で業務に就いていることが求められます。
小規模事業者、中小企業であれば代表者が要件を満たして、その方が引退するまでは基本的に変更しないというパターンが多いのではないでしょうか。
しかし一定規模以上の大手企業、その関連企業様におかれましては取締役の選任を自社ではコントロール出来ないことがあります。公開会社であれば取締役の任期は原則2年ですので、そのタイミングで常勤役員等が退任してしまうと新たに要件を満たす者を選任しないといけません。
建設業を主力とする大手企業・企業グループであれば、役員選任に際しても常勤役員等の維持を重視します。一方、建設業部門が全体事業の一部にとどまる場合、取締役選任に「許可維持の視点」が十分に働かないことも少なくありません。
このため、建設業部門のご担当者にとっては、定時株主総会のたびに「常勤役員の要件を満たす者がいなくなり、いずれ建設業許可を失効してしまうのではないか」と頭を悩ませる場面があるのではないでしょうか。
なので理想としては、新たに就任する取締役の実績に頼ることなく、できれば中長期的に働く従業員の実績を活用して、しかもプロパーで許可を維持したいと思われませんか。実際に、弊所にもそのようなご相談をされる事業者は少なくないように思います。
そこでこの記事では可能な限り従業員の立場で積んだ経験で許可を維持するための手段の重要ポイントをまとめたいと思います。
Contents
常勤役員等の経験として認められる経験
従業員の立場の経験を確認する前に、許可要件である常勤役員等のポイントを簡単に確認しましょう。
許可要件は大きく次の2パターンで合計5つです。
①1人で許可要件を満たす ・イ該当 (1) ②複数人で許可要件を満たす ロ該当 ・ロ該当 (1) |
それぞれ簡単に確認しましょう、
イ該当の(1)
一番オーソドックスなものです。
建設業者の経営経験を指し、登記簿謄本等で5年以上取締役に就いていたかどうかで確認します。該当者が常勤で取締役として就任していれば許可の維持は問題ないです。
また建設業法上の令3条の使用人という従たる営業所の責任者も取締役と同等の経験だと認められ、イ該当の(1)に該当します。
イ該当の(2)
建設業部門の執行役員です。
イ該当の(2)が認められるパターンは取締役会設置会社のみです。執行役員という名称にすれば大丈夫ではないのでご注意ください。
イ該当の(3)
一般的に建設業部門の本部長です。
取締役(会)又はイ該当(2)の執行役員の直下(準ずる地位)で特定業務を補佐していた経験が6年あれば常勤役員として認められます。
ロ該当の(1)
取締役等を直接に補佐した経験が5年と建設業の役員経験が2年以上ある者を取締役等にして、自社の建設業に関する財務、労務、業務の5年以上の実績をもつ者が直接に補佐する体制
ロ該当の(2)
建設業以外の事業の取締役経験が3年と建設業の役員経験が2年以上ある者を取締役等にして、自社の建設業に関する財務、労務、業務の5年以上の実績をもつ者を直接に補佐する体制
それぞれは詳しくリンク先でご確認ください。
まとめると常勤役員等として認められる経験パターンは5つあるということです。
従業員の経験はどれか
常勤役員等の経験として認められる実績を確認しました。
ではこのうち、取締役ではなく従業員の立場でも積める経験で要件として認められるものはどれでしょうか。
該当部分を緑で色付けします。
イ該当の(1)
一番オーソドックスなものです。
~中略~
また建設業法上の令3条の使用人という従たる営業所の責任者も取締役と同等の経験だと認められ、イ該当の(1)に該当します。
イ該当の(2)
建設業部門の執行役員です。
~中略~
イ該当の(3)
一般的に建設業部門の本部長です。
~中略~
ロ該当の(1)
取締役等を直接に補佐した経験が5年と建設業の役員経験が2年以上ある者を取締役等にして、自社の建設業に関する財務、労務、業務の5年以上の実績をもつ者が直接に補佐する
ロ該当の(2)
建設業以外の事業の取締役経験が3年と建設業の役員経験が2年以上ある者を取締役等にして、自社の建設業に関する財務、労務、業務の5年以上の実績をもつ者を直接補佐する
イ該当の(2)の執行役員は別の色で示しました。というのも執行役員は取締役ではないという点では従業員ですが、直ちに認められるわけではなく取締役会設置会社が重要な使用人として選任した場合に認められます。取締役会設置会社でないと認められません。
ではこの記事の本題に戻ると、この緑色の立場で積んだ経験者をなるべく増やすということがプロパー社員でも常勤役員等の候補者になれるという点で重要になります。
どうすれば審査機関に実績を証明できるのでしょうか。
それぞれ確認しましょう。
①令3条の使用人の証明方法
令3条の使用人とは従たる営業所の支店長ですね。
本店以外にも支店があればそこを建設業法上の営業所として登録することで経験が積めます。
経験は申請書の控えや変更届出の表紙で証明します。それ以外に証明方法はないので紛失しないように注意が必要です。
5年以上令3条の使用人経験があれば認められます。
②取締役等に準ずる地位で補佐した経験の証明方法
イ該当の(3)ですね。
取締役の直下の地位で特定業務に従事して、取締役の業務をサポートしていたことを証明します。
証明に必要な書類としては業務分掌規程、職務規程、組織図、人事発令書、稟議書などです。
③自社の建設業に関して5年以上の財務、労務、業務の経験を有する従業員
一人で要件を満たせないロ該当の取締役を直接補佐する従業員が該当します。
自社の建設業に関してそれぞれ5年以上の財務、労務、業務の経験を有することを証明します。
別記事でも言及していますが、この直接に補佐する者に関しての注意点は次の通りです。
・自社の建設業に関する財務、労務、業務の経験した立場はどの立場でもいい(責任者でも平社員でもいい) ・一人で財務、労務、業務の3つを5年で経験した場合でも対象となる(営業所技術者の実務経験と異なり同一期間の経験も重複して認められる) ・財務、労務、業務の5年以上の経験は自社の経験に限る(許可会社に限らない) |
以上踏まえて実績証明に必要な書類は業務分掌規程、組織図、人事発令書、稟議書などが挙げられます。
つまり上記にある①②③の経験者が増えれば増えるほど、従業員の立場の経験のみで常勤役員等の経験証明を満たせるということです。そのために必要なこと、大手企業によくあるハードルを確認しましょう。
実行するためのハードル
理屈では申し上げた通りですが、この記事をご覧になっている方は一定規模以上の大きな企業の建設業部門の担当者さまです。
会社の制度に関わることなので取締役らの承認を得ないと進められません。具体的な論点は会社ごとに異なりますが、私の経験上、実行のハードルになる部分をまとめました。
それぞれ確認しましょう。
(1)最終的には取締役か執行役員に就任する必要がある
常勤役員等は経験を積むことも必要ですが、その経験者が最終的には取締役か取締役会のある会社で建設業部門の執行役員になることが必須です。
つまり会社として、取締役にはプロパー等内部から選ばれることはないのであればそこがハードルとなります。
取締役になれないのであれば、せめて取締役会設置会社かつ執行役員にはなれる体制にすることが重要です。
もちろん執行役員となればもう大丈夫ではありません。現在の会社の体制が建設業法上認められる執行役員体制となっており、それを書類で証明することが大切です。
そのため、事前に審査機関に相談をして現在の体制が認められるものかを確認することも平行して準備することが望ましいでしょう。
(2)一部、特定の許可を一般に変更する
令3条の使用人を増やすことを想定したケースを考えましょう。
例えば、現在は主たる営業所しか許可を受けていない場合でも、別の営業所でも許可を取得する場合にはその従たる営業所には令3条の使用人を選任します。
するとその従たる営業所には営業所技術者を配置しないといけません。
もし本店で許可を受けているすべての業種が特定だとすると、従たる営業所でも特定で取得する必要が出てきます。(同一業種で本店は特定、支店は一般は出来ないため)
となる特定は一級の施工管理技士等でないとなれないなどハードルが高く、営業所技術者の選任が一般より大変になります。
とすれば、実務経験のみで営業所技術者になれる一部の業種は一般に切り替える方が今回の従業員の立場のみで常勤役員等の候補者を増やす趣旨には合致します。会社としての見栄えを考えれば特定で多くの業者が魅力的に映るかもしれません。
しかし常勤役員等を増やしたいのであれば、本当にその特定で取得した業種は特定が必要な工事なのか(下請業者から請求が5000万円以上になるのか)を精査し、必要に応じて一部の業種は一般に変更することが従たる営業所の許可の維持を容易にします。
(3)規程を対外的に理解できるように変更する
証明書類としては稟議書等を挙げましたが、全て社内の書類という点が共通しています。
皆様からすれば社内資料なので当然理解できますし、証明書類として充足していると思うかもしれませんがそうではない可能性があります。
重要なことは審査機関が建設業法上要求する経験を積んでいることを審査して認めることです。
特に規程。
今まで複数社の社内規程を見てきましたが、できることならもっとこのように書いてほしいと思うことは何回かありました。私の考える書き方であれば規程だけで証明資料として済むが、既存の書き方だと稟議書等別途補足書類が必要になるかもしれないといったことです。
もちろん補足書類で証明出来ればいいのですが、理想は人事発令書、組織図、規程の3つで建設業法上の要求を満たせていることを証明できるのがベストでしょう。
社内規程を変更するハードルは存在すると思いますが、説明に時間をかければ変更できるのであれば事前に専門家監修のチェックを受けて社内に稟議をかける方がより安心でしょう。
まとめ
常勤役員等として認められる経験を従業員の立場で積み、常勤役員等になるための手段に必要なこと、そのハードルをまとめました。
一番誤解していただきたくないことは、従業員の立場のままで常勤役員等にはなれないということです。あくまで従業員として経験を積むことで「候補者」にはなれますが、最終的には取締役として登記されるか、取締役会設置会社における常勤の執行役員として選任されることが必須です。
最終的には経験を有する者を取締役として登記し常勤として働くか、取締役会設置会社の建設業部門の常勤の執行役員として選任するか、いずれかは必須ということです。
現在の取締役や執行役員の選任プロセス的に難しい場合には、許可維持の課題として社内へご共有を検討されてみてもいいのではないでしょうか。
大事なことは建設業法上要求している経験を申請する行政機関がどのような形で認められるかを確認した上で規程を定めることです。認められない規程のまま経験を積んでいざ申請するとなっても時間は帰ってきません。導入は慎重すぎるくらいがいいかと個人的には思っています。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。お疲れ様でした。