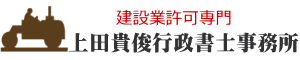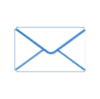アスベストという言葉を聞いたことがある方は少なくないでしょう。
このアスベスト(石綿)は非常に飛散性が高い鉱物で身体に取り入れられると肺がんや中皮腫などを引きおこし、法律上取り扱いには非常に厳しい制限が課せられています。
その取り締まる法令の一つに石綿障害予防規則というものがあります。
内容としては石綿が飛散しないように建物の調査、作業手順及び措置を定めている規則です。
この規則が近年、改正を繰り返し順次新たに取り組むべきことが増えてきています。本規則の改正は全ての建設業者が関係するといっても過言ではなく、実作業をしない施工管理がメインの元請業者も知っておくべきことがたくさんあります。
というのも原則、建設業者には全ての建築物や工作物に対して工事前には石綿が含有していないか調査する義務が課せられており、一定規模以上の工事に関しては石綿があろうがなかろうが元請業者に届出義務が課せられているからです。
この建設作業はドリルで穴をあけてアンカーを打つ程度の作業も含まれますので、商社などが設備を搬入して床にアンカーを打つだけでも対象だと考えられます。なぜ床にドリルに穴を開ける程度のことで調査、報告をしなければならないのでしょうか。
また届出以外に、元請業者としてやるべきことは具体的はどんなことがあるのでしょうか。
結論から言えばやることはたくさんありますが、まずは工事開始前に行う事前調査と届出に関して理解いただくことが望ましいと個人的には思っています。
というのも事前調査と届出は石綿の有無に関わらず必ずやらなければならないからです。
まずは元請業者として行う施工管理、安全配慮義務という観点から石綿障害予防規則を始めとする法令に関してご理解する一助になれば幸いです。
Contents
石綿障害予防規則が厳しい理由・経緯
まず石綿障害予防規則が厳しい理由を納得・理解するため、簡単に法律と石綿と建設業の歴史を確認しましょう。
石綿障害予防規則とは労働安全衛生法という法律の一部です。
労働安全衛生法は、簡単に言えば従業員の健康を維持し、危険から守ることを目的とした法律です。そして規則には具体的な作業手順や必要書類等がが定められています。
つまり石綿障害予防規則とは従業員の健康や危険を脅かす石綿から被害に及ばないための国が定めた作業の手順や必要手続きが定められているということです。
では、なぜ石綿という一部の材料を特定する形で規則が制定されたのでしょうか。
それは石綿が石綿が耐火性、耐熱性、防音性などに優れているため建物や工作物にたくさん取り入れられた歴史があるからです。しかも安価であったために1970年から1990年にかけて年間約30万トンが輸入され、その多くが建築材料に広く使用されてきました。
しかし当時は石綿が健康障害を引き起こすことが知られておらず、大した曝露防止の対策もせずに石綿の除去工事に従事していました。その従事した作業員が長期的な潜伏期間を経て石綿を原因とする肺がんや中皮腫などの健康被害を引き起こしていたことが明らかになり、これは危険だということで石綿の規制が始まったのです。
そのため、日本では平成18年9月1日から、石綿の製造、輸入、使用は原則として全面禁止となりました。逆に言えば、平成18年以前に建築された建物等には当然石綿が含まれているわけです。
これら建築物を何の飛散防止の対策もしないで解体、改修すると健康被害が生じてしまいます。そこで石綿が飛散しないような措置を取らせるために、具体的な作業手順を石綿障害予防規則で定め、建設業者に義務付けているため厳しい規則となっている、これが経緯です。
この石綿障害予防規則の厳格化は現在進行系で進んでおります。理由としては1970年~90年に建てられた建築物の改修、解体工事のピークが2020年から2040年といわれており、まさに今が解体工事のピークが予想されるためです。
商社やエンジニアリング業者が知っておきたい石綿障害予防規則の事前調査と届出
機器や設備を設置、納品する際の作業でも石綿障害予防規則が適用される理由として、石綿がとても人体に危険だからです。
では具体的に建設業者は石綿障害予防規則では何が義務付けられているのでしょうか。
今回は工事の開始前に特化して説明します。
というのも結局最も明らかにしたいことは、建築物に石綿が含有されているかどうかです。石綿が入っていないと事前に分かればすべきことも作業上の手順としては特にないわけです。
ポイントをまとめると次の通りです。
それぞれ確認しましょう。
①工事開始前までに建築物などの事前調査
この規則の目的は石綿による健康障害を防ぐことです。
よって、まず取組むべきことはとにもかくにも、自社が工事する予定の建築物等に石綿が含有されているかどうかを調査することです。
この結果次第で石綿が有るならこうしなさい、無いならこうしなさい、不明ならこうしなさいとっいった形で分岐していきます。
そして一番認識して欲しいことは原則「全ての建築物等に調査義務があること」です。工事金額が安いからしなくていいはありません。
また調査方法も具体的に定められています。
具体的には次の2つです。
(2)目視調査 |
いずれかの方法で調査すればいいわけではなく、必ず両方の調査をしなければなりません。
それぞれ確認しましょう。
(1)書面調査
書面調査とは設計図書や施工記録、仕様書等にて確認する方法です。発注者に設計図書等が残っていないか必ず確認して下さい。
その設計図書等から平成18年9月1日以降に着工した建築物であることが確認出来れば、一般的には石綿が含まれていないと判断出来ます。
ただしガスケット等、一部の材料では適用への猶予期間が設けられていたものもあるので、工作物に関しては設置日だけでは判断出来ません。
製品番号等が特定出来ている場合にはメーカーに問い合わせて石綿の含有濃霧を確認することが求められていますのでご注意下さい。
また平成18年9月1日以前に出来た建築物等で設計図書等から石綿が入っていない(ノンアスベスト)と確認が出来ても安心は出来ません。というのも労働安全衛生法令の適用対象となる石綿等の含有率は数次にわたり変更されているため、材料の製造当時は法令適用対象外として石綿等の使用がないとみなされていたとしても、現行の法令では含有されていないとみなされずに作業の適用対象となる場合もあるからです。
以上が書面調査です。
(2)目視調査
次に目視調査につき説明します。
石綿の調査は書面調査だけでなく現地の目視調査も義務付けられています。
アスベストが含有されているかどうかは、国交省のHPでも目で見るアスベストという資料があるのでご確認ください。書面調査と情報が一致しているか現地で目視調査をします。
更に大事なことは、これら調査は誰でもいいからやればいいというわけではありません。有資格者が調査をする必要があります。(外注でも可能)
有資格者
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者 ※一戸建て住宅・共同住宅の住戸の内部に限定
- 令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
これら資格は講習を受講することで資格者になれますが、受講するためには作業主任者や一定年数以上の実務経験を有する者等の要件が課せられています。
詳しくは石綿障害情報ポータルサイトにてご確認下さい。
まずは事前に書面調査と有資格者が現地調査をする必要があることご理解いただけましたでしょうか。
事前調査の結果、石綿の含有が不明なケース
事前調査の結果、石綿が入っているか不明だった場合を確認しましょう。
その場合にとるべき手段は2つです。
- 分析する
- 石綿が有るとみなして作業する
分析も有資格者により分析することが必要ですので、分析にて進める場合にはご注意ください。
以上、事前調査につき説明しました。
②届出義務の確認
調査をすれば当然、結果がでます。
その結果を報告しないといけません。まず報告する人は発注者です。
どんな工事もどんな結果であっても元請業者から発注者に事前調査の結果を伝える義務があります。
その中でも一定規模以上の工事や危険度の高い石綿含有の結果によっては、発注者だけではなく別途報告する届出義務が課せられます。
(2)飛散性の高い石綿含有結果 |
それぞれ確認しましょう。
(1)工事規模
一定規模以上の建築物等の解体等工事において、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果を都道府県等へ報告する義務があります。この工事を届出対象工事といいます。
ポイントをまとめると次の通りです。
つまり届出対象工事を施工する元請業者は事前調査の結果、石綿の有無に関わらず都道府県に届出す必要があるということです。
機械代金も込で金額を確認するため、基本的には届出が必要になります。
工作物とは一般的に設備が該当します。設備の納品がメインの商社や機器具設置工事業者であっても工作物の解体、改修工事や設置工事が伴えば届出す必要があるということです。
ご注意ください。
(2)飛散性の高い石綿含有結果
(1)は事前調査の結果、石綿の有無に関わらず規模という観点で届出義務が発生します。
対して(2)は飛散性の高い石綿が含有されている場合に発生する届出です。
ここで石綿のレベルにつき確認しましょう。
石綿には飛散性の高さを危険度別にレベル分けしており、レベル1~レベル3と分別されています。このうちレベル1が一番危険です。
事前調査の結果下記のレベル1、レベル2に該当する石綿が含有されていれば別途、特定粉じん排出等作業の届出義務が発生します。
レベル2:石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材 |
このレベル1,2を含む除去工事等を特定工事と呼びます。
つまり特定工事であれば特定粉じん排出等作業の届出が必要になります。提出先は都道府県です。
この特定粉じん排出等作業の届出義務者は元請業者ではなく発注者(ユーザー)になります。とはいえ発注者は元請業者の事前調査の結果報告をベースに工事開始の14日前までに回答する義務があるので、元請業者としてはその期日に間に合うように発注者に伝える必要があるので、期日も把握しておきましょう。
またレベル1,2が含有される場合、届出はそれだけではありません。
石綿の除去工事の計画届出を労働基準監督署に工事開始の14日前に届出す必要があります。これは元請業者が作業計画等を作成して提出する義務があるのでご注意下さい。
以上が工事開始までにすべき届出です。
まとめ
石綿が関係する工事につき元請業者がすべきことをまとめました。
実際に作業をする場合には作業手順なども定められておりますが、エンジニアリング系の元請業者として知っておくべきこととして事前調査と届出義務を把握していただきたくまとめました。
石綿は非常に危険であり、規制前の石綿除去作業が原因で罹患した方々向けの給付金制度(アスベスト給付金)があります。それは国が自らの責任を認めた形で償いの意味も込めて設けられた制度です。
それくらい危険なので厳しく規制されているということご認識いただけますと幸いです。
エンジニアリング系の事業者の場合、建築や土木系事業者よりも石綿に関しては関係ないといった意識を持ってしまうかもしれませんが、実際には深く関係があるのでご認識ください。